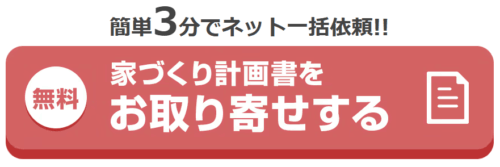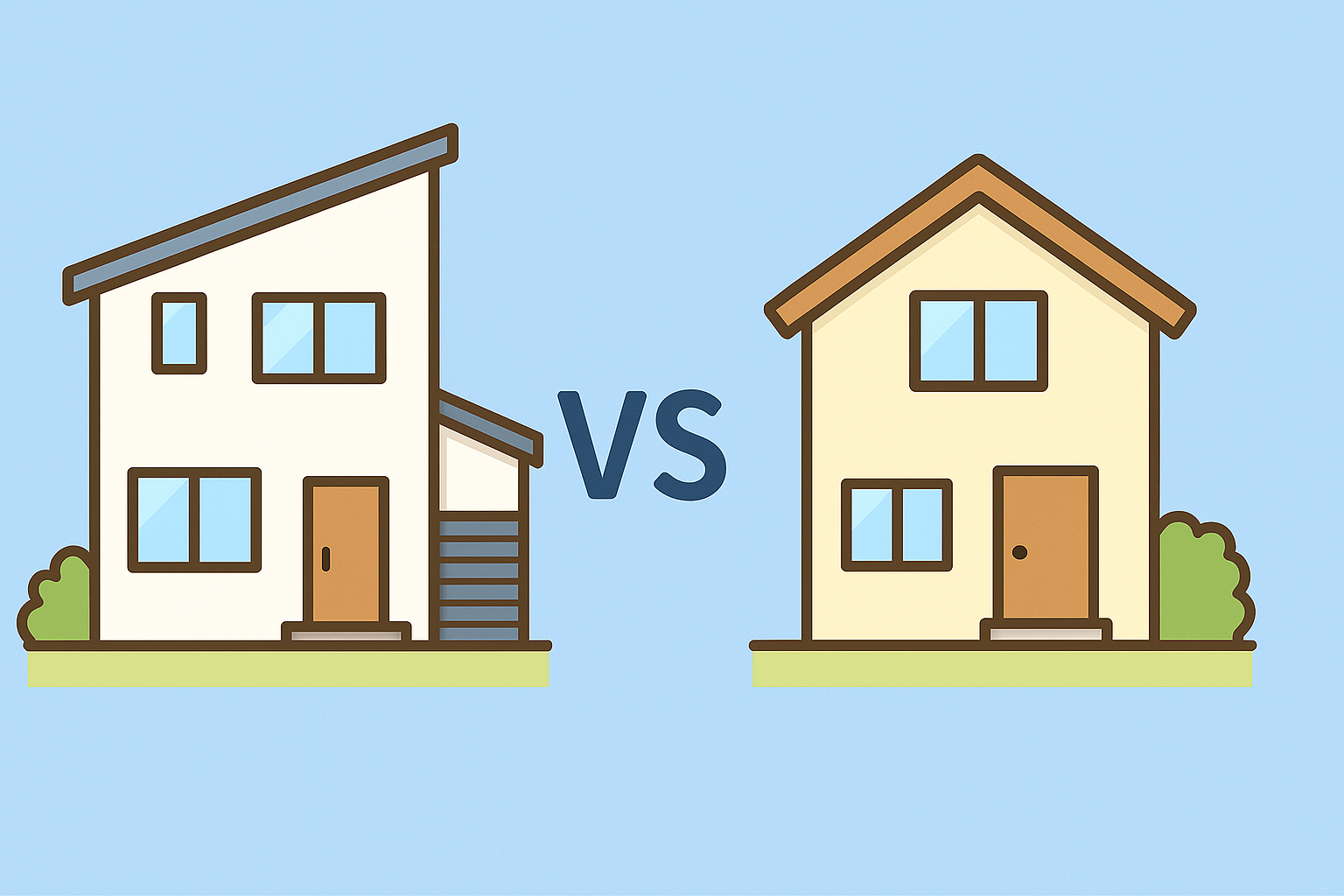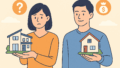「そろそろマイホームが欲しいな」と考え始めたとき、夢の注文住宅への期待が膨らむ一方で、「完成まで一体どれくらいの時間がかかるんだろう?」「子どもの小学校入学までに間に合うかな?」といった、漠然とした期間への不安が頭をよぎる方は少なくありません。
家づくりは、ほとんどの方にとって一生に一度の大きなプロジェクト。だからこそ、スケジュール感を把握し、計画的に進めることが成功の鍵を握ります。
この記事では、注文住宅の建築期間に関するあらゆる疑問に答えます。土地探しから始める場合の平均的な期間から、家が完成するまでの具体的な流れ、各工程にかかる日数の目安、そして「後悔しないために」知っておきたい期間が伸びる原因と短縮のコツまで、専門的な知見を交えながら徹底的に解説します。
結論からお伝えすると、注文住宅が完成するまでの期間は、土地探しから始める場合は平均1年〜2年、すでに土地が決まっている場合は平均10ヶ月〜15ヶ月が目安です。ただし、これはあくまで平均的な数字。依頼する会社やプラン内容によっては最短6ヶ月で完成することもあれば、こだわりの設計や不測の事態で2年以上かかることもあります。
この記事を最後まで読めば、ご自身の状況に合わせたリアルな建築期間をイメージできるようになり、漠然とした不安が具体的な計画へと変わるはずです。後悔しない家づくりの第一歩として、まずは「期間」の全体像を正しく理解することから始めましょう。
【結論】注文住宅の建築期間は「土地あり/なし」で大きく変わる
注文住宅の建築期間を考える上で、最も重要なのが「建築用の土地を所有しているかどうか」です。この条件によって、家づくり全体のスケジュールは半年から1年以上も変わってきます。
土地探しから始める場合:平均1年〜2年
まだ土地をお持ちでない場合、家づくりのプロジェクトは土地探しからスタートします。この土地探しが、全工程の中で最も期間が読めない部分です。希望のエリア、広さ、価格、法規制などの条件をすべて満たす土地がすぐに見つかるとは限りません。
運良く数ヶ月で見つかることもあれば、理想を追い求めて1年以上かかるケースも珍しくありません。そのため、土地探しを含めたトータルの期間は、平均して1年〜2年、長い場合はそれ以上を見込んでおく必要があります。
土地が決まっている場合:平均10ヶ月〜15ヶ月
すでに建築予定地が決まっている、あるいは親から譲り受けた土地がある場合、スケジュールは格段に立てやすくなります。この場合の建築期間は、住宅会社との打ち合わせ開始から引き渡しまで、平均して10ヶ月〜15ヶ月が目安となります。
土地に関する不確定要素がないため、より具体的な計画を立てて進めることが可能です。
【注意】最短6ヶ月も可能だが、条件が重要
「そんなに待てない!」という方もご安心ください。条件が整えば、最短6ヶ月〜8ヶ月で注文住宅を建てることも不可能ではありません。これを実現するには、以下のような条件が揃っていることが前提となります。
・プランがある程度規格化された住宅を選ぶ(セミオーダーや規格住宅)
・住宅会社との打ち合わせがスムーズに進み、意思決定が早い
・天候や資材調達に問題が発生しない
ただし、期間を短くすることだけを優先すると、仕様や間取りで妥協が生まれたり、後々の後悔につながったりする可能性もあります。スピードと満足度のバランスを考えることが大切です。
建築期間も相談できる!
\資料請求で今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
【全体像】注文住宅が完成するまでの流れと期間(全6ステップ)
では、具体的にどのような工程を経て家は完成するのでしょうか。ここでは、注文住宅が完成するまでの一般的な流れを6つのステップに分け、それぞれの「やること」と「期間の目安」を解説します。
| ステップ | 工程 | 期間の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 相談・準備期間 | 2~3ヶ月 | 予算計画、情報収集、家族でのイメージ共有、要望の整理 |
| ② | 土地探し期間 | 3ヶ月~1年以上 | 不動産会社訪問、土地の見学、候補地の選定・契約 |
| ③ | 会社選び・契約期間 | 2~3ヶ月 | ハウスメーカー・工務店の比較検討、プラン提案、見積もり取得、請負契約 |
| ④ | 設計・プランニング期間 | 3~6ヶ月 | 詳細な間取り・仕様の打ち合わせ、建築確認申請 |
| ⑤ | 建築工事期間 | 4~6ヶ月 | 地鎮祭、基礎工事、上棟、内外装工事、設備工事 |
| ⑥ | 完成・引き渡し期間 | 約1ヶ月 | 竣工検査、登記手続き、住宅ローン実行、引き渡し |
①【相談・準備期間】イメージ固めと情報収集(2~3ヶ月)
家づくりのスタート地点です。まずは家族で「どんな家に住みたいか」「どんな暮らしがしたいか」を話し合い、イメージを共有します。
SNSや雑誌で好みのデザインを探したり、住宅展示場を訪れたりして、理想の家の解像度を高めていきましょう。同時に、自己資金や住宅ローンを考慮した大まかな予算計画を立てることも重要です。
②【土地探し期間】家づくりの期間を最も左右する(3ヶ月~1年以上)
土地がない場合は、このステップが最初の大きな関門です。不動産情報サイトで探すだけでなく、地域の不動産会社や、土地探しもサポートしてくれるハウスメーカー・工務店に相談するのが効率的です。
良い土地はすぐに買い手がつくため、日頃からアンテナを張り、迅速に決断できる準備をしておくことが求められます。
③【会社選び・契約期間】パートナー選定(2~3ヶ月)
土地が決まったら(あるいは土地探しと並行して)、家づくりのパートナーとなる建築会社を選びます。複数の会社からカタログを取り寄せ、モデルハウスを見学し、担当者と話してみましょう。
2〜3社に絞り込んで具体的なプランと見積もりを依頼し、内容、価格、担当者との相性などを総合的に比較して契約先を決定します。
資料請求で信頼できる担当を見つける!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
④【設計・プランニング期間】理想をカタチにする(3~6ヶ月)
契約後、いよいよ具体的な設計の打ち合わせが始まります。間取りはもちろん、壁紙、床材、キッチンやお風呂の設備、コンセントの位置に至るまで、決めるべきことは山積みです。通常、1〜2週間に1回のペースで打ち合わせが行われます。
すべての仕様が確定したら、自治体や指定確認検査機関に「建築確認申請」を提出します。この申請に許可が下りるまでには、書類に不備がない場合でも、法律で定められた審査期間として最大35日(特定の構造計算が必要な場合は最大70日)を要するため、1ヶ月前後は見ておく必要があります。
⑤【建築工事期間】いよいよ着工から竣工まで(4~6ヶ月)
建築確認の許可が下りると、いよいよ工事が始まります。工事の安全を祈願する「地鎮祭」から始まり、「基礎工事」「上棟(骨組みの組み立て)」、屋根や外壁の工事、そして内装や設備の工事へと進んでいきます。
この期間は、現場に時々足を運び、家が形になっていく様子を見守るのも楽しみの一つです。
⑥【完成・引き渡し期間】最終チェックと手続き(約1ヶ月)
すべての工事が完了すると「竣工」となります。施主と施工会社が立ち会い、図面通りにできているか、傷や不具合がないかをチェックする「竣工検査(施主検査)」を行います。
問題がなければ、残金の支払いや建物の登記手続き、住宅ローンの本実行などを経て、ついに鍵が渡され「引き渡し」となります。
【新設】どこに頼むかで変わる!依頼先別の建築期間の傾向
注文住宅の建築期間は、どこに依頼するかによっても傾向が変わります。ハウスメーカー、工務店、設計事務所、それぞれの特徴と期間の関係性を理解し、ご自身の希望に合ったパートナーを選びましょう。
| 依頼先 | 設計の自由度 | 建築期間 | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスメーカー | △(規格内) | 短い傾向 | 比較的高め | 品質が安定。工期が明確で計画を立てやすい。 |
| 工務店 | 〇(比較的自由) | 会社による | 幅広い | 地域密着型。柔軟な対応が期待できるが、工期は規模や体制次第。 |
| 設計事務所 | ◎(非常に高い) | 長い傾向 | 設計料+工事費 | デザイン性や唯一無二のプランを追求。設計に時間をかける。 |
スピードと安定感の「ハウスメーカー」
全国展開している大手ハウスメーカーは、建材の生産から施工までシステム化・規格化されているのが特徴です。そのため、プランがある程度決まれば工事の段取りがスムーズで、工期は比較的短く、計画通りに進みやすい傾向にあります。品質も安定しており、工期の遅延リスクを減らしたい方、転勤や入学などで引き渡し時期が明確に決まっている方におすすめです。
自由度と期間のバランスが良い「工務店」
地域に根ざした工務店は、ハウスメーカーほどの規格化はされていませんが、その分、施主の要望に柔軟に対応してくれるのが魅力です。建築期間は、その工務店の規模や年間の施工棟数、職人の手配状況によって変わります。
ハウスメーカーよりは長くなる傾向がありますが、設計事務所ほどではありません。自由度と期間のバランスを取りたい方に向いています。
設計にじっくり時間をかける「設計事務所」
唯一無二のデザインや、複雑な土地の形状を活かしたプランなど、設計の自由度を最大限に追求したいなら設計事務所という選択肢があります。
建築家は施主のライフスタイルや価値観を深くヒアリングし、ゼロからプランを創り上げるため、設計・プランニング期間が最も長くなるのが特徴です。家づくりそのものを楽しみ、時間に余裕がある方におすすめです。
もちろん「どこでも」資料請求可能!
\今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
なぜ?注文住宅の建築期間が予定より伸びる“3つ”の代表的な原因
どんなに綿密に計画を立てても、様々な理由で建築期間が予定より伸びてしまうことがあります。ここでは、代表的な遅延の原因を3つのカテゴリーに分けて解説します。
【施主側の原因】打ち合わせ中の仕様変更・意思決定の遅れ
最も多いのが、施主側の都合による遅延です。特に設計の打ち合わせ段階で、「やっぱり間取りを変えたい」「床材を違うものにしたい」といった大幅な変更があると、図面の修正や見積もりの再作成、建材の再発注などで時間がかかります。また、夫婦間での意見がまとまらず、仕様決定が遅れることも工期に影響します。
【施工会社側の原因】人手不足や複数現場のかけもち
建設業界全体で課題となっている職人不足も、工期遅延の一因です。特に小規模な工務店では、複数の現場をかけもちしているケースも多く、予定通りに職人を手配できないと工事が進まないことがあります。信頼できる会社かどうか、年間の施工実績や体制を事前に確認することも大切です。
【外部要因】天候不順、資材不足、行政手続きの遅延
施主にも施工会社にも責任のない、外部の要因で遅延することもあります。基礎工事や上棟は天候に大きく左右されるため、長雨や台風、積雪などで工事がストップすることがあります。また、記憶に新しい「ウッドショック」のような世界的な資材の供給不足や価格高騰、半導体不足に起因する給湯器や一部の住宅設備の納期遅延も、工期に影響を与えるリスクとして挙げられます。これらの問題は一時期より落ち着きを見せていますが、依然として不測の事態が起こる可能性はゼロではないため、外部環境のリスクとして認識しておくことが大切です。
後悔しないために!建築期間を短縮・管理する4つのコツ
予定通りに、あるいは少しでも早く理想の家を完成させるためには、施主側の準備と心がけが非常に重要です。ここでは、誰でも実践できる4つのコツをご紹介します。
【コツ1:準備段階】理想の家の「優先順位リスト」を家族で作成する
打ち合わせが始まってから迷わないように、事前に家族で「絶対に譲れないこと」「できれば実現したいこと」「妥協できること」をリストアップし、優先順位をつけておきましょう。
例えば、「リビングの広さは絶対に譲れないが、2階の書斎はなくてもいい」といった具合です。このリストがあるだけで、意思決定のスピードが格段に上がります。
【コツ2:会社選び】担当者との相性とコミュニケーションの速さを重視する
家づくりは、建築会社の担当者との二人三脚です。こちらの質問や要望に対するレスポンスが早いか、親身に相談に乗ってくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。
契約前に担当者の対応力を見極めることが、後のスムーズな進行につながります。
【コツ3:設計段階】「標準仕様」を上手に活用し、複雑な設計は避ける
ハウスメーカーや工務店が設定している「標準仕様」は、性能とコストのバランスが良く、納期も安定している建材や設備が選ばれています。
すべてを特注品にするのではなく、標準仕様をうまく活用することで、コストを抑えつつ工期を短縮できます。また、あまりに複雑なデザインや特殊な工法は、工期が長くなる原因になることも覚えておきましょう。
【コツ4:最終手段】工期が最優先なら「セミオーダー・規格住宅」も検討する
「とにかく早く入居したい」という明確な期限がある場合は、フルオーダーの注文住宅だけでなく、ある程度プランや仕様が決まっている「セミオーダー住宅」や「規格住宅」も視野に入れると良いでしょう。選択肢が絞られている分、打ち合わせ期間が短縮され、全体の工期も大幅に短くなります。
後悔しない資料請求の決定版!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
期間の読み間違いが招く!よくある後悔ポイント3選
「なぜスケジュール管理がそんなに大事なの?」と思うかもしれません。それは、期間の読み間違いが、お金や暮らしに直結する深刻な後悔につながる可能性があるからです。
【金銭的な後悔】仮住まいの家賃、つなぎ融資の金利が膨らむ
最も直接的なダメージが金銭面です。工事が遅延すれば、現在お住まいの賃貸住宅の家賃や、建て替え中の仮住まいの費用が余分にかかります。
また、土地の購入代金や着工金などを自己資金以外で支払うために利用する「つなぎ融資」は、一般的な住宅ローンより金利が高いため、期間が延びるほど利息負担が増えてしまいます。
【計画的な後悔】子どもの入学・転園、仕事の復帰に間に合わない
「子どもの小学校入学に合わせて4月までに入居したかったのに、工事が遅れて間に合わなかった…」というのは、非常によく聞く失敗談です。学区が変わってしまうため、一時的に遠くの学校へ通わせるか、最悪の場合は転校を余儀なくされることも。
また、産休・育休からの仕事復帰のタイミングなどに合わせて計画していた場合も、生活設計が大きく狂ってしまいます。
【住み心地の後悔】期間に焦って決めた間取り・設備にずっと不満が残る
工期に追われ、「もうこれでいいや!」と焦って間取りや設備を決めてしまうと、住み始めてから「やっぱりコンセントの位置が不便だった」「もっと収納を確保すればよかった」といった不満が出てきがちです。
家はこれから何十年も住む場所。期間を気にするあまり、住み心地という本質的な価値を犠牲にしてしまうのは、最大の後悔と言えるでしょう。
注文住宅の建築期間に関するよくある質問(Q&A)
信頼できる会社に資料請求する!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
まとめ:計画的なスケジュール管理が、後悔しない家づくりの第一歩
今回は、注文住宅の建築期間について、全体の流れから期間が変動する要因、そして後悔しないためのコツまでを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 期間の目安: 土地探しからなら1年〜2年、土地ありなら10ヶ月〜15ヶ月。
- 流れの把握: 全6ステップの流れと各期間を理解し、全体像をつかむことが重要。
- 遅延リスク: 期間が伸びる原因は、施主側・施工会社側・外部要因の3つがあることを知る。
- 成功のコツ: 事前の優先順位決めと、信頼できるパートナー選びが鍵。
注文住宅の建築期間は、単なる時間の問題ではありません。それは、あなたの資金計画やライフプラン、そして何より、これから何十年と続く「住み心地」にまで深く関わってきます。
この記事を読んで、家づくりの全体像とスケジュール感がつかめたら、次はいよいよ具体的なアクションに移る番です。
「自分たちの場合は、どんな会社が合っているんだろう?」
「複数の会社のプランや見積もりを比較してみたい」
そう感じたら、まずは複数の住宅会社からカタログや資料を取り寄せてみることから始めましょう。1社だけでなく、ハウスメーカー、工務店など様々なタイプの会社を比較することで、各社の特徴や強みが分かり、自分たちの理想を叶えてくれるベストなパートナーを見つけやすくなります。
当サイト「家づくり比較」では、簡単な入力だけで全国の優良企業から一括で資料請求が可能です。あなたの後悔しない家づくりの、確かな第一歩として、ぜひご活用ください。
複数社から資料請求するなら…
\今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】