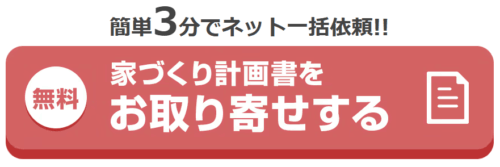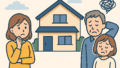「デザインも間取りも自由に決めたいから、建てるなら絶対に注文住宅!」
「でも、何千万円もかける大きな買い物。絶対に失敗だけはしたくない!」
注文住宅は、自分たちの理想を形にできる、まさに「夢のマイホーム」です。しかしその一方で、自由度が高いからこそ無数にある選択肢の中から、すべてを自分で決めていかなくてはなりません。その過程で思わぬ落とし穴にはまり、「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまう方が少なくないのも、また事実です。
この記事は、「注文住宅を建てる!」と心に決めたあなたが、最高の家づくりを実現するために生まれました。
家づくりを経験した1,000人以上の先輩たちのリアルな体験談(ブログ、口コミ)を徹底的に分析し、多くの人が「後悔したこと」「失敗したこと」、そしてそこから見えてきた「成功への秘訣」を、ランキング形式で余すところなく解説します。
さらに、家づくり初心者の方が迷わないための「全手順ロードマップ」や、お金・設備に関する「よくある質問」にも具体的にお答えします。
この記事を最後まで読めば、あなたは先輩たちの貴重な失敗から学び、後悔しない家づくりのための「正しい知識」と「具体的なアクションプラン」を手に入れられるはずです。あなたの不安を解消し、自信を持って家づくりへの第一歩を踏み出すお手伝いをします。
【本音で語る】注文住宅の後悔・失敗談ランキングTOP15
自由設計だからこそ起こりがちな「後悔ポイント」。
1,000人以上の体験談から見えてきた、特に声の多かった失敗談をランキング形式でご紹介します。「なぜ失敗したのか?」という原因と、「こうすればよかった」という具体的な対策をセットで学び、あなたの家づくり計画に潜むリスクを回避しましょう。
第1位:【お金】甘い資金計画で想定外の500万円オーバー

最も多くの人が後悔していたのが、やはり「お金」の問題です。特に、予算オーバーに関する失敗談が後を絶ちません。
どんな失敗?
ハウスメーカーから提示された「建物本体価格」だけを見て資金計画を立ててしまい、契約後に判明した様々な費用に驚愕するケースです。外構工事や地盤改良費、給排水の引き込み工事といった「付帯工事費」、さらに登記費用や各種保険料、税金などの「諸費用」が積み重なり、気づけば当初の予算を数百万単位でオーバー。結果的に住宅ローンの返済計画が大きく狂い、暮らしを圧迫してしまうのです。
見積もりでは2,000万円だったのに、最終的に2,500万円を超えました。外構や地盤改良費が思ったより高かったです。最初に総額でいくらかかるのか、もっとしっかり確認すべきでした。
対策は?
家づくりにかかる費用は、「総額」で考えるクセをつけましょう。必ず3社以上のハウスメーカーや工務店から「総額での相見積もり」を取得し、冷静に比較検討することが、予算オーバーを防ぐための絶対的な鉄則です。見積書の内訳もしっかり確認し、不明な点は遠慮なく質問しましょう。
第2位:【間取り】自由すぎた結果、家事と生活がしにくい家に…

注文住宅の醍醐味である間取りの自由設計。しかし、この自由さが裏目に出てしまうことも少なくありません。
どんな失敗?
デザイン性や開放感を優先するあまり、日々の生活動線や家事動線が考慮されていない間取りになってしまう失敗です。例えば、「洗濯機を回す(洗面所)→洗濯物を干す(2階バルコニー)→たたむ(リビング)→しまう(各部屋のクローゼット)」という一連の動線が分断され、毎日の家事が大きなストレスになるケースは非常に多く聞かれます。
リビング階段は開放的で素敵だと思いましたが、空調の効きが悪いうえに、テレビの音や話し声が2階まで筒抜け。子どもが勉強に集中できないみたいで、ドアをつければよかったと後悔しています。
対策は?
間取り図の上だけで考えず、朝起きてから夜寝るまで、家族一人ひとりの動きを具体的にシミュレーションしてみましょう。間取り図に色違いのペンで動線を書き込んでみると、「ここがぶつかるな」「ここの移動は無駄が多いな」といった問題点が驚くほどよく見えてきます。
第3位:【収納】量も場所も大失敗!とりあえずの収納計画
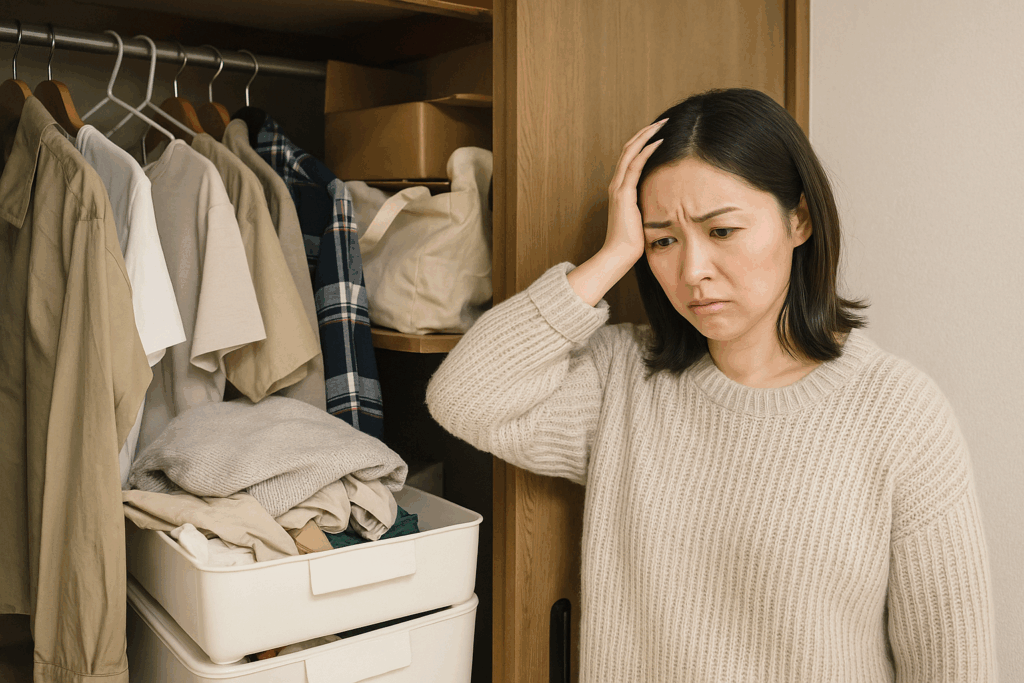
「収納はたっぷり作ったはずなのに、なぜか家が片付かない…」これも注文住宅で非常によくある後悔ポイントです。
どんな失敗?
収納の「総量」だけを気にしてしまい、「どこで何を使うか」という視点が抜け落ちてしまう失敗です。例えば、掃除機をしまっておく場所が1階の奥にしかないと、2階を掃除するのが億劫になります。また、奥行きが深すぎるパントリーを作った結果、奥に入れたものが取り出せず、賞味期限切れの食品が溜まる「死蔵品置き場」になってしまうケースも典型的です。
広いパントリーは憧れでしたが、奥行きが深すぎて奥のものが取り出せず、結局手前の使いやすい部分しか使っていません。これなら奥行きの浅い棚を壁一面に作ればよかったです。
対策は?
収納計画の基本は「適材適所」です。「今ある荷物の量+将来増える分(20%程度)」を収納量の目安としつつ、「どこで」「誰が」「何を」使うのかを考え、使う場所のすぐ近くに適切なサイズの収納を作ることが成功の鍵です。
第4位:【コンセント・スイッチ】図面だけでは気付けなかった配置ミス

どんな失敗?
いざ家具や家電を置いたらコンセントが隠れてしまった。ダイニングテーブルでホットプレートを使いたいのに遠くて延長コードが必須。ベッドに入ってから照明を消すのに、わざわざ入口まで行かなくてはならない、などです。
対策は?
設計段階で、テレビや冷蔵庫、ベッドといった大きな家具の配置をあらかじめ図面に書き込んでもらいましょう。そして、スマホはどこで充電するか、掃除機はどこから電源を取るか、といった具体的な生活シーンを思い浮かべながら、必要な場所と数をリストアップすることが重要です。
第5位:【窓】採光と断熱のバランス、設計士任せの落とし穴
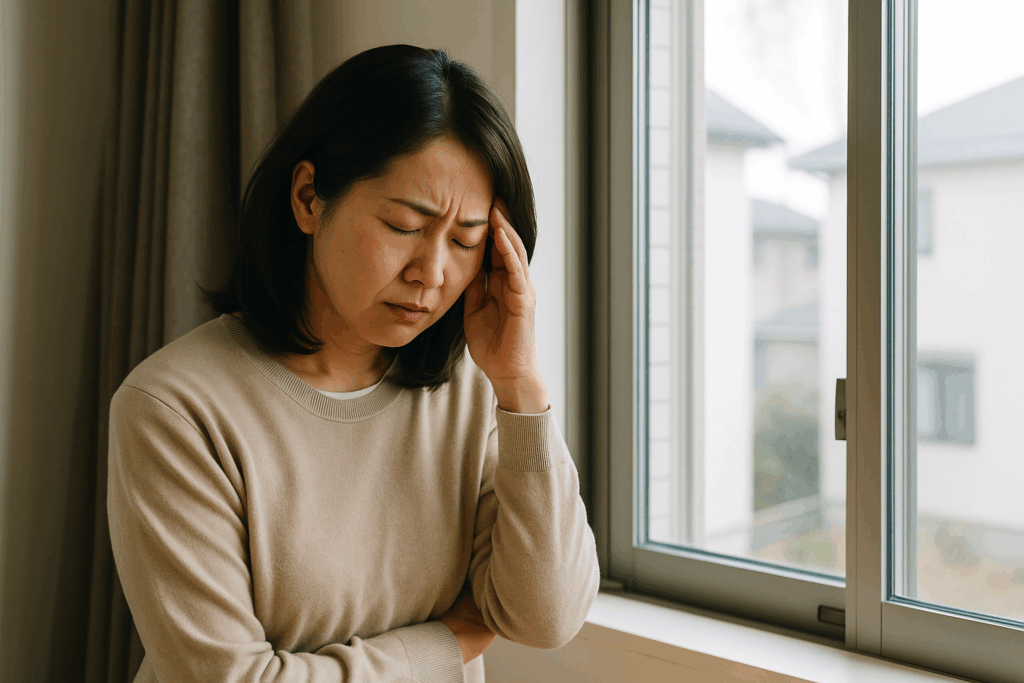
どんな失敗?
開放感のある大きな窓に憧れたが、西日が強すぎて夏は灼熱地獄に。逆に北側の部屋は一日中薄暗く、冬は結露がびっしり。見た目重視でFIX窓(開かない窓)を多用したら、風通しが悪くジメジメする家になってしまった、などです。
対策は?
方角ごとの日当たりの特性を理解し、窓の大きさや性能(ペアガラス/トリプルガラスなど)、庇(ひさし)の有無を検討することが不可欠です。設計士任せにせず、「この窓は風を通すため」「この窓は安定した光を取り入れるため」と、一つ一つの窓に役割を持たせる意識で打ち合わせに臨みましょう。
第6位:【キッチン】理想の高さ・広さと現実の使い勝手のギャップ

どんな失敗?
ショールームで見た素敵なアイランドキッチン。しかし実際に導入すると、リビングから調理台が丸見えで常に片付けておかないと落ち着かない。また、ワークトップの高さを奥様の身長に合わせたら、旦那様には低すぎて腰が痛くなってしまった、というケースもあります。
対策は?
キッチンの高さは、主に使う人の「身長÷2+5cm」が使いやすい高さの目安として広く知られています。複数人で使う場合は、スリッパを履くかなども考慮して、ショールームで実際に立ってみて高さを体感することが大切です。生活感を隠したいなら、手元が少し隠れる「腰壁」を設けるのも有効です。
第7位:【外構・庭】後回しにした結果、予算もデザインも中途半端に
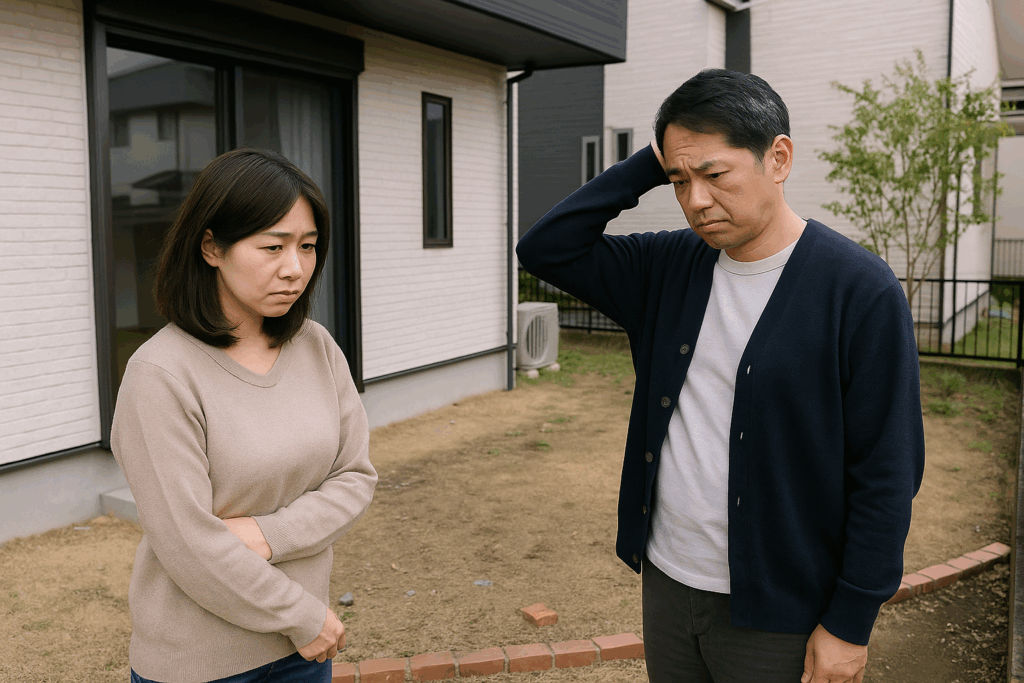
どんな失敗?
建物のことで頭がいっぱいで、外構(門、アプローチ、駐車場、フェンスなど)の予算をしっかり確保していなかった。家が完成してから考え始めたら、思いのほか高額で、結局砂利を敷くだけの寂しい見た目になってしまった。
対策は?
外構は「家の顔」です。建物の設計と同時に、外構計画もスタートさせましょう。建物と外構をトータルでデザインすることで、統一感のある美しい住まいが実現します。予算も必ず初期段階で「外構費」として確保しておくことが重要です。
第8位:【打ち合わせ】言った言わない問題!担当者任せにしたツケ

どんな失敗?
打ち合わせで「伝えたはず」の要望が、完成した家には反映されていなかった。「大丈夫です、やっておきます」という担当者の言葉を信じていたら、議事録に残っておらず、追加費用を請求された。
対策は?
打ち合わせの際は、必ず毎回議事録を作成してもらい、双方で内容を確認した証を残すようにしましょう。面倒でも、この一手間が後の「言った言わない」トラブルを防ぐ最大の防御策になります。また、重要な要望はメールなど記録に残る形で伝えることも有効です。
第9位:【壁紙・クロス】小さなサンプルと大きな壁の印象の違い

どんな失敗?
小さなサンプルでは素敵に見えた柄物の壁紙が、広い面積に貼ってみると、ごちゃごちゃして落ち着かない印象になってしまった。逆に、真っ白を選んだつもりが、照明の下では青白く見えて寒々しい部屋になってしまった。
対策は?
可能であれば、A4サイズ以上の大きなサンプルを取り寄せましょう。そして、実際に使う部屋の壁に当てて、自然光や照明の下で朝・昼・晩と見え方を確認することが失敗しないコツです。
第10位:【照明】オシャレだけど暮らしに合わないプラン

どんな失敗?
間接照明だけのオシャレなリビングにしたが、実際に生活してみると全体的に薄暗く、子どもが本を読んだり勉強したりするには光量が足りなかった。ペンダントライトのデザインは素敵だけど、ホコリが溜まりやすく掃除が大変。
対策は?
照明計画は、「主照明(部屋全体を照らす)」と「補助照明(手元などを照らす)」を組み合わせて考えましょう。生活シーンに合わせて明るさを調整できる「調光・調色機能」付きの照明を選ぶと、満足度が格段に上がります。
第11位:【寝室・子ども部屋】将来を見据えなかった広さの失敗
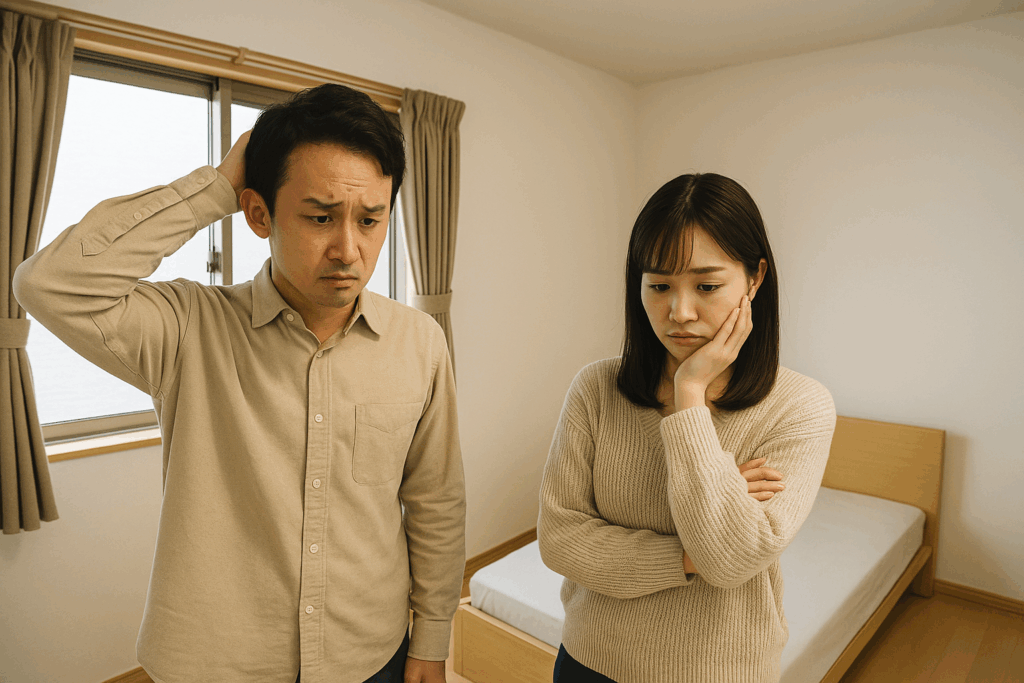
どんな失敗?
今は夫婦2人だからと、寝室を広く取りすぎた。将来、親との同居や介護が必要になった時に、間仕切りして部屋を増やせるようにしておけばよかった。子どもが小さいうちは一部屋で十分だったが、成長してプライベートな空間が必要になった時に対応できない。
対策は?
家族のライフステージは変化します。20年後、30年後の家族構成や暮らしを想像し、将来的に間仕切りを設置したり、逆に壁を取り払って広く使えたりするような、可変性のある間取りを検討しておくことが重要です。
第12位:【お風呂・洗面所】見栄えと掃除のしやすさはトレードオフ

どんな失敗?
ホテルライクな黒いバスタブやカウンターは格好良いが、水垢が目立ってしまい、掃除を少しでも怠ると汚らしく見えてしまう。デザイン性の高いボウル一体型でない洗面台は、隙間に水が跳ねてカビの原因に。
対策は?
デザイン性だけでなく、日々のメンテナンス性も必ず考慮しましょう。ショールームのスタッフに「掃除のしやすさ」について質問したり、実際に使っている人の口コミを調べたりすることが有効です。
第13位:【ベランダ・バルコニー】理想と現実。作ったけど使わない空間

どんな失敗?
広いバルコニーでバーベキューを夢見ていたが、近所の目や煙が気になって一度も使っていない。洗濯物を干すためだけに、高額な費用と固定資産税を払い続けている状態に。
対策は?
そのバルコニーで「本当に何をするのか」を具体的に考えましょう。洗濯物を干すだけなら、浴室換気乾燥機やガス衣類乾燥機などを導入し、バルコニーをなくす、あるいは小さくするという選択も賢い判断です。
第14位:【防音・音漏れ】自由設計だからこそ配慮が必要だった家族の音
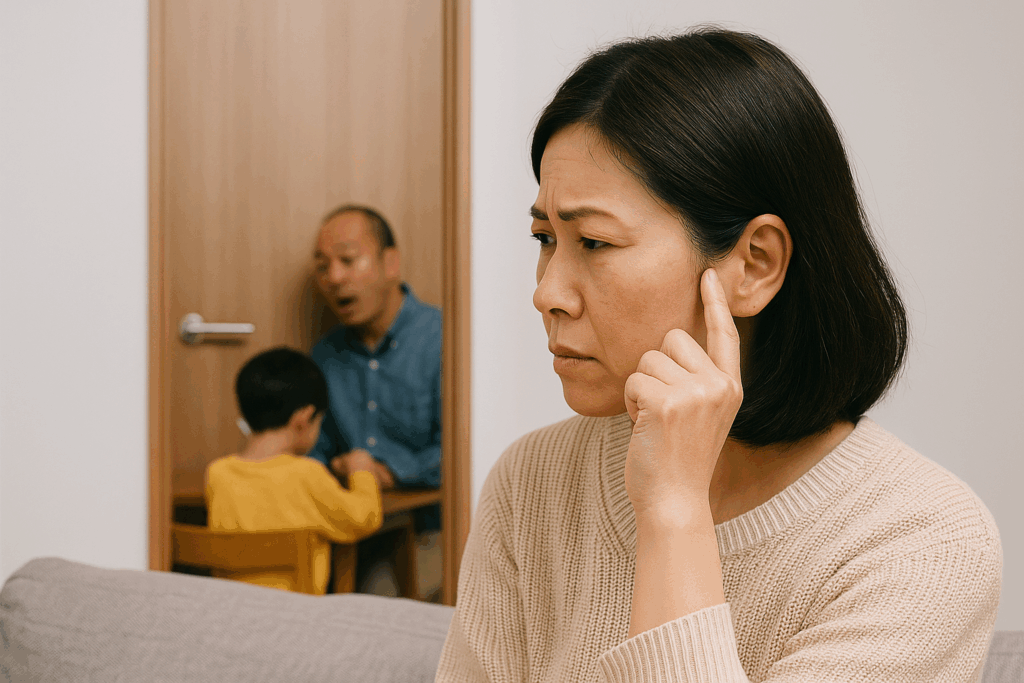
どんな失敗?
寝室の隣にトイレを配置してしまい、夜中に流す水の音で目が覚めてしまう。吹き抜けやリビング階段によって、2階で寝ている子どもがリビングのテレビの音で起きてしまう。
対策は?
音の問題は、間取り計画の初期段階で配慮することが重要です。寝室などの静かに過ごしたい部屋の隣には、トイレや浴室、子ども部屋などを配置しないようにしましょう。壁の中に吸音材を入れる、二重窓にするなどの対策も有効です。
第15位:【近隣環境】建物ばかりに気を取られ…土地選びの妥協

どんな失敗?
日当たりの良さだけで土地を決めたが、すぐ隣にアパートが建ち、日当たりが悪くなったうえにプライバシーもなくなった。平日は静かだったのに、休日は近くの道路の交通量が多くてうるさい。
対策は?
土地は家と違って動かせません。契約前に、曜日や時間帯を変えて何度も現地に足を運ぶことが鉄則です。周辺に空き地がある場合は、将来何が建つ可能性があるのかを役所で確認する(用途地域を調べる)ことも重要です。
後悔しない家づくりの第一歩は、正しい情報を、できるだけたくさん集めることから始まります。あなたの夢のマイホーム実現のために、まずは気軽に情報収集からスタートしてみてはいかがでしょうか。
失敗しないためには資料請求が鉄板!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
【これさえ見ればOK】注文住宅の全手順ロードマップ
「家づくりって、何から手をつければいいの?」そんな初心者のあなたのために、情報収集から引き渡しまでの全ステップを、期間の目安と先輩からのアドバイス付きで完全ガイドします。
| ステップ | 主な内容 | 期間の目安 | 先輩からのアドバイス |
|---|---|---|---|
| STEP1 | 情報収集&イメージ固め | 検討開始〜3ヶ月 | まずは家族会議!どんな暮らしがしたいか、絶対に譲れない条件は何かを話し合おう。SNSや雑誌で好きなデザインの写真をスクラップしておくと、後でイメージを伝えやすい。 |
| STEP2 | 資金計画&予算決定 | 1ヶ月 | 自己資金はいくらか、親からの援助はあるかを確認。住宅ローンの事前審査を受けておくことで、自分たちが借りられる金額がわかり、その後の計画がスムーズに進む。 |
| STEP3 | 土地探し | 3ヶ月〜1年以上 | 土地探しと建築会社探しは並行して進めるのが効率的。良い土地はすぐに売れてしまうので、決断力も大切。地域の不動産会社とハウスメーカーの両方に相談しよう。 |
| STEP4 | 建築会社の選定・比較 | 2〜3ヶ月 | 住宅展示場や完成見学会に積極的に参加しよう。最低でも3社以上から相見積もりを取り、価格だけでなく、担当者との相性や会社の家づくりへの考え方を比較することが重要。 |
| STEP5 | 設計・プランの打ち合わせ | 3〜6ヶ月 | 人生で一番密度の濃い打ち合わせ期間。後悔しないよう、疑問や要望は遠慮せずに伝えよう。毎回、議事録で決定事項を確認することがトラブル防止の鍵。 |
| STEP6 | 着工〜完成 | 4〜6ヶ月 | 地鎮祭や上棟式など、家づくりのイベントを楽しもう。可能であれば、定期的に現場に顔を出し、職人さんたちに感謝を伝えると、現場の士気も上がり丁寧な仕事に繋がることも。 |
| STEP7 | 完成・引き渡し | – | 建物の傷や汚れ、不具合がないかを確認する「施主検査」は、専門家(ホームインスペクター)に同行してもらうと安心。ここからが本当のスタート! |
後悔しない家づくりの第一歩は、正しい情報を、できるだけたくさん集めることから始まります。あなたの夢のマイホーム実現のために、まずは気軽に情報収集からスタートしてみてはいかがでしょうか。
まずは気軽に資料請求してみる!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
体験者が本音で回答!付けてよかった設備 vs 意外といらなかった設備
無数にあるオプション設備。先輩たちの「採用して正解!」「これは不要だったかも…」というリアルな声は、あなたの設備選びにおける最高の判断材料になります。
【生活が激変】付けてよかった設備・オプション BEST5
- 食器洗い乾燥機(深型)
言わずと知れた家事の時短王。共働き世帯や子育て世代からは「これなしの生活は考えられない」との声が多数。手洗いよりも節水になる点も魅力です。 - 浴室換気乾燥機
雨の日や花粉の季節、梅雨時期の洗濯ストレスから解放されます。「外に干したくない」派にも必須の設備。 - タッチレス水栓(キッチン・洗面所)
手が汚れていても蛇口を触らずに水が出せるため、衛生的で掃除も楽。こまめに水を止められるので節水効果も期待できます。 - 玄関のスマートキー
子どもを抱いていたり、両手が買い物袋で塞がっていたりしても、鍵を探す手間なくドアを開けられる快適さは想像以上。一度使うと元には戻れません。 - リビング床暖房
エアコンのように風が出ないため、ホコリが舞いにくく空気が乾燥しにくいのが特徴。足元からじんわりと部屋全体が暖まる心地よさは、冬の暮らしの質を格段に向上させます。
【本当に必要だった?】いらなかった設備・オプション
- 2階のミニキッチン
朝の準備が楽になるかと思ったが、結局使うのは1階のメインキッチンばかり。掃除の手間だけが増えてしまった、という声が目立ちます。 - 凝ったデザインの照明
見た目はオシャレでも、複雑な形状のものはホコリが溜まりやすく掃除が非常に大変。シンプルなダウンライトで十分だった、という現実的な意見も。 - 天窓(トップライト)
採光には有効ですが、「夏は暑すぎる」「雨音がうるさい」「将来の雨漏りやメンテナンスが心配」といったデメリットを指摘する声も少なくありません。
後悔しない家づくりの第一歩は、正しい情報を、できるだけたくさん集めることから始まります。あなたの夢のマイホーム実現のために、まずは気軽に情報収集からスタートしてみてはいかがでしょうか。
信頼できるメーカーも全部わかる!
\しかも今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】
【注文住宅限定】体験談でよくある質問(Q&A)
注文住宅を建てる際に、誰もが一度は抱く素朴な疑問。先輩たちの体験談も交えながら、Q&A形式でお答えします。
Q. 注文住宅って、諸費用込みの総額でいくらくらい見ればいいですか?
A. 一概には言えませんが、体験談では「建物本体価格+800万~1,000万円」を総額の目安としている声が多く聞かれます。公的機関の調査(※)によると、2022年度の注文住宅(建物のみ)の全国平均建設費は約3,717万円でした。これに土地代や諸経費が加わるため、総額では4,000万円台〜5,000万円台になるケースが一般的です。ただし、これはあくまで目安。必ず「総額での見積もり」を複数社から取得することが重要です。
※出典:住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」
Q. 私の年収で、注文住宅は建てられますか?
A. 建てられます。重要なのは年収の額そのものよりも、「無理のない資金計画」を立てられるかどうかです。金融機関やファイナンシャルプランナーが用いる考え方の一つに、借入額の目安を「年収の5〜7倍」とするものがあります。例えば年収400万円なら2,000万〜2,800万円が目安です。ただし、これは家族構成や貯蓄、金利などによって大きく変動する参考値です。多くの金融機関で無料のローン相談が可能ですので、専門家と一緒にご自身の状況に合った資金計画を立てることを強くお勧めします。
Q. 50歳からでも注文住宅は建てられますか?
A. はい、問題なく建てられます。実際に50代で「終の棲家」として、これまでの経験を活かしたこだわりの注文住宅を建てる方は多くいらっしゃいます。その際は、住宅ローンの完済年齢を考慮して自己資金の割合を増やす、将来の身体の変化を見据えてバリアフリー設計(手すりの設置、段差の解消など)を標準で取り入れる、といった若い世代とは異なる視点での計画が成功の鍵となります。
Q. ハウスメーカー選びで失敗しないための、体験者が語る一番のポイントは?
A. 圧倒的に多いのが「担当者との相性」という答えです。どんなに評判の良いハウスメーカーでも、あなたの要望を正確に汲み取り、プロとして的確な提案をしてくれない担当者では、満足のいく家は建ちません。複数の会社の担当者と実際に話し、「この人になら、人生最大の買い物を任せられる」と心から思えるパートナーを見つけることが、何よりも重要だと言えるでしょう。
Q. 「建売にしとけばよかった…」と後悔した人の体験談で、一番多い理由は何ですか?
A. 「決めることが多すぎて疲れてしまった」という声が最も多く聞かれます。注文住宅は、間取りから壁紙、コンセントの位置一つまで、すべて自分で決める必要があります。このプロセスを楽しめる人には最高ですが、「こだわりは特にないから、プロに任せたかった」「打ち合わせに時間を取られすぎた」と感じる方にとっては、大きな負担になることがあります。自分の性格が、注文住宅のプロセスに向いているかを見極めることも大切です。
まとめ:最高の注文住宅は、最高のパートナー(建築会社)選びから始まる
ここまで、1,000人以上の体験談から見えてきた注文住宅の後悔ポイントと、それを乗り越えて成功するための秘訣を詳しく解説してきました。
数々の失敗談からわかる、たった一つのシンプルな事実。それは、家づくりの後悔のほとんどが「情報不足」と「比較検討の不足」から生まれる、ということです。
そして、この二つの不足を解消し、最高の注文住宅という夢を叶えるために、あなたが今すぐ始めるべき最も重要なアクションが一つだけあります。
それは、「複数の会社を比較して、心から信頼できるパートナーを見つけること」です。
一社だけの話を聞いて決めてしまうのは、あまりにも危険です。A社では常識のことが、B社では非常識かもしれません。C社なら、あなたの悩みを解決する、もっと素晴らしい提案をしてくれるかもしれません。
「でも、一社ずつ展示場を回るのは大変…」
そう感じたあなたにこそ、ぜひ活用してほしいのが、無料の一括カタログ請求サービスです。自宅にいながら、スマホ一つで複数のハウスメーカーや工務店のカタログをまとめて取り寄せることができます。
たくさんのカタログを比較して、様々な会社の家づくりへの想いやデザイン、性能に触れてみましょう。たくさんの実例を見ることは、あなたの理想の家を具体的にする、最高のヒントになるはずです。
カタログを見て、少しでも気になる会社が見つかったら、そこから初めてオンライン相談や展示場訪問といった次のステップに進めば良いのです。
後悔しない家づくりの第一歩は、正しい情報を、できるだけたくさん集めることから始まります。あなたの夢のマイホーム実現のために、まずは気軽に情報収集からスタートしてみてはいかがでしょうか。
信頼できるメーカー資料を全部無料で!
\今なら全員にプレゼント!/
👉成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り
(小冊子16ページPDF)
【PR】