都心へのアクセスが良く、緑豊かで閑静な住宅街が広がる世田谷区。注文住宅を建てるエリアとして絶大な人気を誇ります。
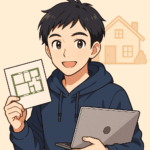
ゆうた
しかし、その優れた住環境は、実は他のエリアにはない独自の厳しい建築規制によって守られていることをご存知でしょうか。
「専門用語ばかりで、何から調べればいいのか全くわからない」
「3階建てやビルトインガレージは、本当に実現できるのだろうか?」
家づくりを考え始めた多くの方が、こうした「規制の壁」に直面し、大きな不安を抱えています。せっかくの夢のマイホーム計画が、情報不足で後悔に終わってしまうことほど悲しいことはありません。
この記事は、そんなあなたのための「世田谷区の建築規制・完全攻略ガイド」です。
家づくりのプロの視点から、全ての規制の土台となる「用途地域」の調べ方から、最も複雑な「高さ制限」、そして「3階建て」のような希望を叶えるための具体的なヒントまで、図解のように分かりやすく、体系的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたの土地でどんな家が建てられるのかが明確にイメージでき、数ある建築会社の中から本当に信頼できるパートナーを見つけるための確かな知識が身につきます。さあ、規制を正しく理解し、最高の家づくりへの第一歩を踏み出しましょう。
【基本のキ】すべての土台!世田谷区の「用途地域」をまず知ろう
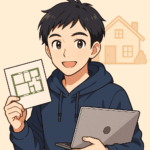
ゆうた
家づくりを規制するルールの根幹、それが「用途地域」です。 まずはこの基本から押さえましょう。
そもそも「用途地域」とは?住環境を守るためのゾーニング
用途地域とは、計画的な街づくりのために、エリアごとに「建てられる建物の種類・大きさ・高さ」などを定めたルールのことです。 例えば、「住宅街」「商業地」「工業地」といったゾーニング(区分け)をイメージすると分かりやすいでしょう。これにより、住宅街の真ん中に大きな工場が建つのを防ぎ、それぞれの地域の特性に合った環境が守られています。
世田谷区の最大の特徴:「第一種・第二種低層住居専用地域」が約6割
世田谷区の住環境がなぜ良いのか。その答えがここにあります。区の面積の約6割が、最も規制が厳しい「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」で占められています。これは、主に低層住宅の良好な環境を守るための地域で、建物の高さや用途が厳しく制限されます。このおかげで、日当たりの良い、静かで落ち着いた街並みが保たれているのです。
【最重要】あなたの土地の用途地域を調べてみよう!
家づくりの計画は、ご自身の土地(または検討中の土地)の用途地域を知ることから始まります。これは専門家でなくても、インターネットで簡単に調べることができます。世田谷区の用途地域を調べる方法世田谷区が提供している地理情報システム「せたがやi-map」を使いましょう。
- 「せたがやi-map」にアクセスします。
- 利用規約に同意し、地図画面に進みます。
- 画面上部の「地図選択」から「都市計画(用途地域等)」を選びます。
- 住所検索で調べたい場所を表示すると、地図が色分けされ、その土地の用途地域や建ぺい率・容積率の基準値、さらに詳細なルールを定めた「地区計画」の有無などが表示されます。
あなたの知りたい情報が手に入る!
\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/ 
世田谷で人気のハウスメーカーの資料を
一括請求する【PR】
【図解で納得】世田谷区の家づくりで押さえるべき5大建築規制
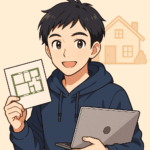
ゆうた
用途地域がわかったら、次はいよいよ具体的な規制の内容です。 特に重要な5つのポイントを、できるだけ分かりやすく解説します。
① 建物の大きさに関わる「建ぺい率」と「容積率」
建物の規模を直接決める、最も基本的な数値です。建ぺい率(建蔽率)
敷地面積に対する「建物を真上から見たときの面積(建築面積)」の割合です。例えば、100㎡の土地で建ぺい率が50%なら、建築面積は50㎡までとなります。庭や通路など、敷地内に空地を確保し、日当たりや風通しを良くする目的があります。
容積率
敷地面積に対する「建物の全フロアの床面積の合計(延床面積)」の割合です。例えば、100㎡の土地で容積率が100%なら、延床面積は100㎡まで。1階60㎡・2階40㎡といった家が建てられます。人口密度をコントロールし、道路や下水道などのインフラがパンクしないようにする目的があります。
知らないと損!建ぺい率・容積率の緩和措置建築基準法で定められた一定の条件を満たすと、基準より大きな家を建てられる「緩和措置」があります。
- 角地緩和: 特定の条件を満たす角地は、建ぺい率が10%加算されます。
- 耐火建築物緩和: 防火地域内で耐火建築物を建てる場合、建ぺい率が10%加算されることがあります。
- 容積率の不算入: 延床面積の計算から除外できる部分もあります。(例:ビルトインガレージは延床面積の1/5まで、地下室は住宅部分の床面積合計の1/3まで不算入など)
② 最も複雑!建物の高さを決める「高さ制限」
世田谷区の家づくりで最も設計士の頭を悩ませるのが、この高さ制限です。複数のルールが重なっているため、非常に複雑です。絶対高さの制限
第一種・第二種低層住居専用地域では、原則として建物の高さを10mまたは12mに抑えなければなりません。どちらが適用されるかは、用途地域や地区計画によって定められています。斜線制限
道路や隣地の日照・採光・通風を確保するため、建物の上部を斜めに削るように形を制限するルールです。3種類あります。-
- 道路斜線制限: 道路の反対側の境界線から、一定の勾配で引かれる斜線の中に建物を収める必要があります。
- 隣地斜線制限: 隣地の境界線上の一定の高さから、一定の勾配で引かれる斜線の中に建物を収める必要があります。
- 北側斜線制限: 低層住居専用地域で特に重要なルール。北側の隣地の日当たりを守るため、北側の境界線から引かれる斜線が最も厳しくなっています。家の形が北側から斜めに削られるようなデザインになるのは、この規制のためです。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) 冬至の日(一年で最も影が長くなる日)を基準に、周辺の敷地に一定時間以上影を落とさないように、建物の高さを制限するルールです。
③ 建物の仕様が決まる「防火・準防火地域」の規制
駅周辺や幹線道路沿いは、火災の延焼を防ぐため「防火地域」や「準防火地域」に指定されていることがあります。| 規制の種類 | 特徴 | 建物への影響(例) |
|---|---|---|
| 防火地域 | 最も規制が厳しいエリア。駅前など。 | 原則として、耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)にする必要がある。 |
| 準防火地域 | 防火地域に準ずるエリア。市街地など。 | 一定の基準を満たせば木造でも建築可能だが、窓は網入りガラス、外壁は防火性能のあるサイディングにするなど、仕様が制限される。 |
④ 隣家との距離を決める「外壁後退」と「敷地面積の最低限度」
良好な住環境を守るため、「地区計画」などによって、さらに詳細なルールが定められている場合があります。外壁後退距離
エリアによっては、「建物の外壁を、敷地の境界線から1mまたは1.5m離しなさい」といったルールが定められていることがあります。これにより、隣家との間に空間が生まれ、圧迫感がなく風通しの良い街並みが形成されます。敷地面積の最低限度
土地を細かく分割しすぎて、小さな家が密集するのを防ぐルールです。例えば「70㎡未満の敷地には家を建てられない」といった決まりがあり、これもエリアごとに数値が異なります。 これらのルールは、お住まいのエリアの「地区計画」によって内容が大きく異なるため、必ず個別に確認が必要です。⑤ 世田谷区ならではの独自ルール「景観」と「みどり」
法律だけでなく、区独自の条例も家づくりに影響します。景観づくり条例
国分寺崖線周辺や成城、田園調布など、特に景観が重視されるエリアでは、建物の色やデザイン、塀の作り方などに配慮が求められる場合があります。みどりの条例
一定規模以上の建物を建てる際には、敷地内に定められた割合以上の緑化(植樹など)が義務付けられています。世田谷の条例もクリアした
あなたの理想を手に入れるチャンス!
\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/ 
世田谷で人気のハウスメーカーの資料を
一括請求する【PR】
【希望を叶えるヒント】規制の中で理想の家を建てるには?
「規制が厳しいのはわかったけど、希望は叶えたい!」その通りです。規制は乗り越えるためにあります。
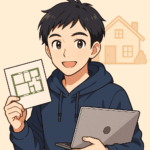
ゆうた
プロの設計士は、これらのルールの中で施主の希望を叶えるための知恵と工夫を凝らします。
Case1:どうしても「3階建て」の家が欲しい!
世田谷区で3階建てを建てるのは不可能ではありませんが、土地選びが非常に重要です。第一種・第二種低層住居専用地域では、絶対高さ10m/12mの制限があるため、現実的には困難です。 狙い目は、第一種中高層住居専用地域や準住居地域など、高さ制限が比較的緩やかな用途地域の土地です。
その上で、斜線制限をクリアするために、屋根の形を工夫したり、半地下を活用したりといった設計力が必要になります。
Case2:狭い土地でも「広く開放的な家」に住みたい!
狭小地こそ、設計力が試される舞台です。規制の中で空間を最大限に活用するアイデアはたくさんあります。空間を有効活用する設計テクニック
- 地下室/半地下: 容積率緩和の対象になるため、+αの部屋(書斎やシアタールームなど)を作れます。
- スキップフロア: 床の高さを半階ずつずらすことで、空間に変化と広がりが生まれ、壁のない一体的な空間を作れます。
- 吹き抜け/高窓: 縦への広がりを演出し、視線が上に抜けることで開放感が生まれます。狭小地の採光問題も解決できます。
- 屋上利用: 高さ制限の範囲内であれば、屋上をプライベートな庭(屋上緑化)として活用することも可能です。
Case3:日当たりが良く、明るいリビングが理想!
特に北側斜線が厳しい土地でも、諦める必要はありません。- 2階リビング: 1階よりも日当たりと眺望を確保しやすいため、家族が集まるLDKを2階に配置するのは非常に有効な手段です。
- 天窓(トップライト)/中庭: 建物の中心部など、窓からの光が届きにくい場所に直接光を落とすことができます。プライバシーを確保しながら、家全体を明るくすることができます。
あなたの理想をのぞいてみませんか?
\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/ 
世田谷で人気のハウスメーカーの
資料を一括請求する【PR】
世田谷区の注文住宅に関するよくある質問(Q&A)
Q. 結局、第一種低層住居専用地域の高さ制限は何メートルですか?
A. 原則として10mですが、地区計画などにより12mに定められているエリアもあります。土地ごとにルールが異なるため、ご自身の土地に適用される正確な高さを「せたがやi-map」や役所の窓口で必ず確認してください。
Q. 自分の土地の建ぺい率・容積率が知りたいです。
A. 世田谷区の「せたがやi-map」で用途地域を調べると、その地域に定められた建ぺい率・容積率の基準値が表示されます。例えば「50/100」とあれば、建ぺい率50%・容積率100%が基準となります。
Q. 外壁後退の距離は必ず守らないといけないのですか?
A. はい、地区計画などで定められている場合は必ず守る必要があります。ただし、このルールがないエリアもあります。距離も「1m」や「1.5m」などエリアによって異なるため、ご自身の土地のルールを個別に確認することが非常に重要です。
Q. 規制について、どこに相談すれば良いですか?
A. 一般的な規制内容の確認であれば、世田谷区役所の「建築審査課 相談窓口」で教えてもらえます。しかし、ご自身の希望(「この土地で3階建ては可能か?」など)を叶えるための具体的な設計プランについては、世田谷区での建築実績が豊富な工務店や設計事務所に相談するのが最も確実でスムーズです。
Q. 規制が厳しい土地は、避けた方が良いのでしょうか?
A. 一概にそうとは言えません。規制が厳しいということは、それだけ住環境が将来にわたって守られている証拠でもあります。むしろ、その規制を熟知し、逆手にとって魅力的なプランを提案してくれる設計士や工務店を見つけることができれば、資産価値の高い、素晴らしい家を建てることが可能です。
注文住宅に強いハウスメーカーや工務店をカンタンに資料請求できる方法について、こちらの記事にまとめていますので参考にしてみてください!
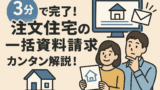
しつこい営業なく注文住宅の一括資料請求をたった3分で完了して理想を手に入れる方法
「家づくり、何から始めれば…」と悩むあなたへ。最短3分であなたの理想が手に入る注文住宅の資料請求術を解説します。無料の間取りプランで人気会社をカンタンに比較できるので、忙しい方でも安心。最適なハウスメーカー探しの決定版です。
複雑な規制を乗り越えるパートナー!世田谷区でおすすめの工務店・ハウスメーカー15選
ここまで解説した通り、世田谷区の家づくりは、法律や条例との対話そのものです。これらの複雑な条件を正確に読み解き、あなたの理想を最高の形で実現してくれる、信頼できるプロのパートナーを見つけることが何よりも重要です。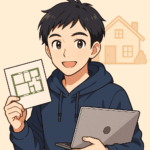
ゆうた
ここでは、世田谷区の厳しい規制を熟知し、狭小地や3階建て、デザイン性の高い住宅など、様々な実績を持つ工務店・ハウスメーカーをご紹介します。
1. 株式会社アーキテクト・ディベロッパー(旧:株式会社ホープス)
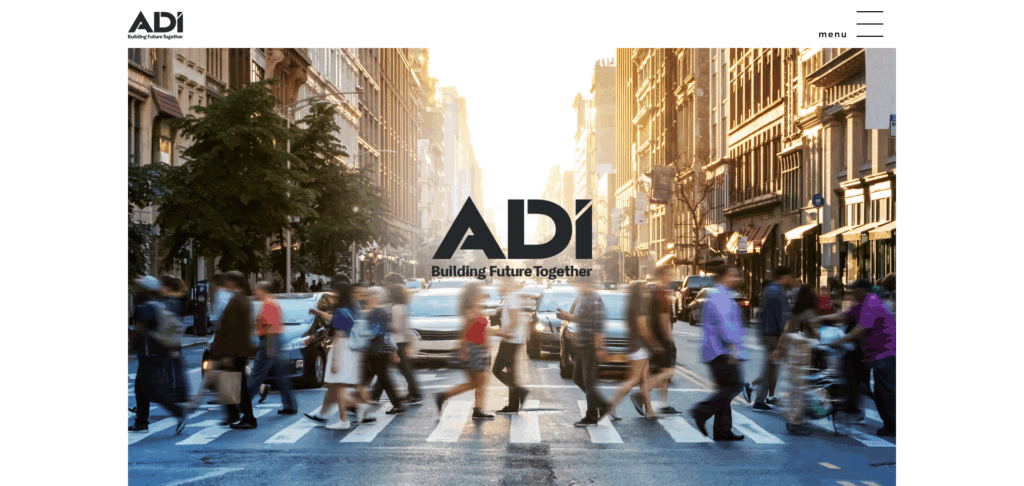
- キャッチコピー: 東京の狭小住宅・デザイン住宅ならおまかせ
- 特徴:
- 狭小地・変形地での建築が得意
- 建築家と建てるデザイン性の高い家
- リライフスタイルを提案
2. ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)
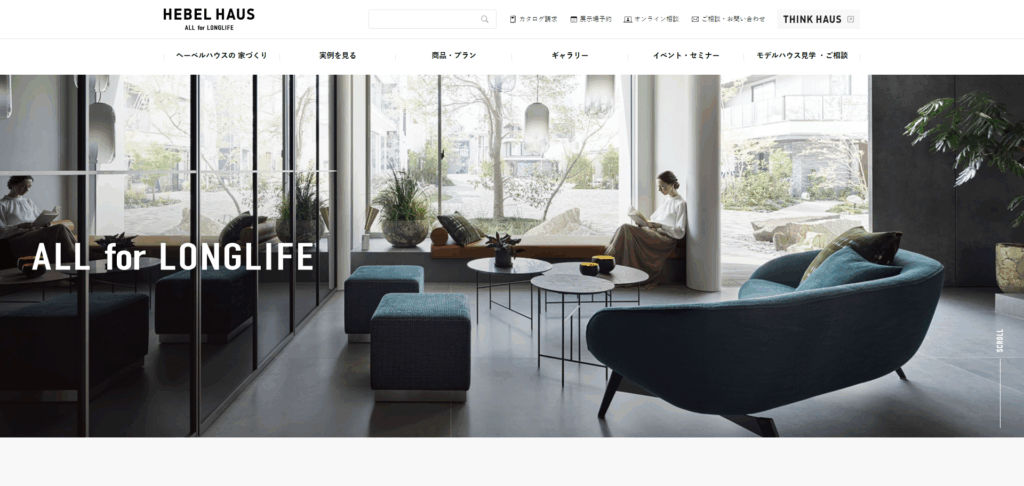
- キャッチコピー: 災害に強く、60年間安心が続くロングライフ住宅
- 特徴:
- 災害に強い躯体構造
- 60年間の長期保証と点検システム
- 重鉄制震・デュアルテックラーメン構造
人気のハウスメーカーで
あなたの理想を見てみませんか?
\一括無料請求で今なら全員にプレゼント!/ 
人気のハウスメーカーの資料を一括請求する【PR】
まとめ:信頼できるプロと一緒に、世田谷区で最高の家づくりを
今回は、世田谷区で注文住宅を建てる際に避けては通れない「建築規制」と「用途地域」について、詳しく解説しました。この記事のポイント
- 世田谷区の約6割は、住環境を守るための「低層住居専用地域」である。
- 建物の大きさは「建ぺい率・容積率」、高さは「絶対高さ・斜線制限・日影規制」で決まる。
- 防火規制や、エリアによっては外壁後退・緑化条例など、守るべきルールは多岐にわたる。
- 規制は障壁ではなく、工夫次第で「3階建て」や「広いリビング」も実現可能である。
実際の規制は、あなたの土地ごとに定められた「用途地域」や「地区計画」によって細かく異なります。 これらの複雑なパズルを、あなた一人で解く必要はありません。
規制を正確に理解し、法律や条例の範囲内であなたの希望を最大限に引き出すのが、家づくりのプロである工務店や設計事務所の仕事です。 むしろ、パートナー選びこそが、世田谷区での家づくり成功の最大の鍵と言えるでしょう。
「この会社なら、難しい条件の中でもきっと面白い提案をしてくれるはずだ」そう思えるような、信頼できるパートナーを見つけてください。
まずは、気になる会社のカタログを取り寄せ、どんな家づくりをしているのか、どんな想いを持っているのかを知ることから始めてみませんか。
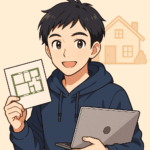
ゆうた
複数の会社を比較検討することで、あなたの理想を叶えてくれる最高のパートナーがきっと見つかるはずです。
\ 最短3分! /
未来の我が家をのぞいてみる
クリックして、家づくりの第一歩を踏み出そう

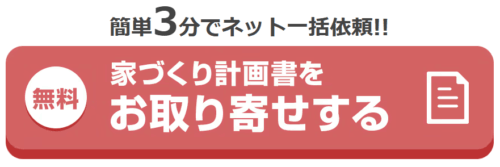
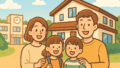
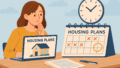
そんな時に出会ったのがホープスさんでした。私達の趣味やライフスタイルを丁寧にヒアリングしてくれて、まるで自分のことのように真剣に考えてくれました。結果、デザインも予算も大満足の家が完成!打ち合わせの度にワクワクして、本当に楽しい家づくりでした。